間近で拝観できる鎌倉時代の阿弥陀如来像
西宮市歴史資産活用活性化協議会は、毎年11月、西宮市内にある文化財を順次公開。国の重要文化財に指定されている昌林寺と明徳寺の本尊も、それぞれ16日(日)、22日(土)に4時間だけ公開されます。いずれも鎌倉時代後半に流行した「安阿弥様(あんなみよう)」の特徴を示す木造阿弥陀如来立像。その姿をすぐ近くで鑑賞できる貴重な機会です。
昌林寺には浄土教を大成した高僧の像も
JR「西宮」駅から南へ歩いて約10分。多田源氏ゆかりの昌林寺は974(天延2)年、多田満仲の子、円覚坊源賢僧都の開基と伝えられています。阪神・淡路大震災で被災し、再建された本堂には本尊の木造阿弥陀如来立像。その両脇に木造観音菩薩像と木造勢至菩薩像が控えます。
仏像の様式は、快慶の作風に影響を受けた「安阿弥様」で、温和で優美な雰囲気ながら写実性に富んでいます。「納衣(のうえ)には截金(きりかね)文様が施されています」と、学芸員を務める西宮市文化財課の東原直明さん。「金の線で彩る截金文様は細い上に、仏像全体が長い年月を経て黒味を帯びているので、かなり近づかないと分かりません。特別公開時は、普段は近寄れない所まで入れるので、ぜひ截金文様を見つけてください」
もう一体、見逃せないのが、同じ本堂内にある木造善導大師坐像。こちらも国指定重要文化財です。「善導大師は中国唐代の高僧で、中国で浄土教を大成した方。口を少しだけ開けて名号を称(とな)える姿は写実に徹している一方で、お顔は童子のような愛嬌のある表情を浮かべています」。2つの性質が作品の中に混然一体となっているのは、14世紀ごろの彫刻の特徴だそうです。

-1024x673.jpg)

穏やかな中にも玉眼が鋭い阿弥陀さま
もう一つの木造阿弥陀如来立像は、西宮北部の静かな山里、山口町に立つ明徳寺に安置されています。山門をくぐり、手入れの行き届いた庭を左右に見ながら進めば、威風堂々としたたたずまいの本堂に至ります。
浄土真宗大谷派の寺院で、その名前は1615(慶長19)年に東本願寺の教如上人から賜ったと伝わります。建立年や縁起は実のところ不明だとか。「1686(貞享3)年の火災で文書を全て焼失してしまったので、はっきりしたことが分からないのです。ご本尊はその特徴から鎌倉時代に作られたものだといわれています」と、住職の中尾哲さんは話します。
本堂の正面奥、金色に彩られた内陣に木造阿弥陀如来立像は立っています。穏やかで絵画的な「安阿弥様」の特徴をよく示し、衣紋も繊細な線で刻まれています。「丸い古風なお顔がとても穏やかで慈しみを感じます。衣紋の彫刻も本物の衣のように柔らかい雰囲気で、どうやって彫ったのだろうと感心させられます」と中尾さん。その一方で玉眼が用いられた目は鋭く、りりしさも感じさせます。
明徳寺の阿弥陀さまも、特別公開時は通常より近くから拝観できます。国の重要文化財を至近距離で見ることができる年に1度のチャンス。金の極細線で施された文様、表情をつくる眉や目などのパーツ、幾つもの曲線で形成された衣紋など、彫刻作品としての素晴らしさを堪能しましょう。



日時:①11月16日(日)②11月22日(土)いずれも10:00~14:00
場所:①西宮市津門西口町14-12②西宮市山口町上山口1-4-5
アクセス:①JR「西宮」駅から徒歩約10分②阪急バス「山口センター前」下車徒歩約5分 ※いずれも見学者専用駐車場はありません。公共交通機関を利用してください
問い合わせ:西宮市歴史資産活用活性化協議会(西宮市文化財課内)
TEL:0798-33-2074
HP:https://nishi-rekishisan.jp/
マップ(昌林寺):https://maps.app.goo.gl/Cj1yZmDm97nFJWB76
マップ(明徳寺):https://maps.app.goo.gl/7meewDXVFF1o6vQG6






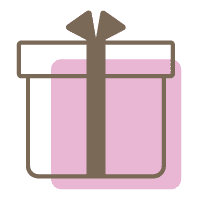

-1-300x300.jpg)
-300x298.png)






